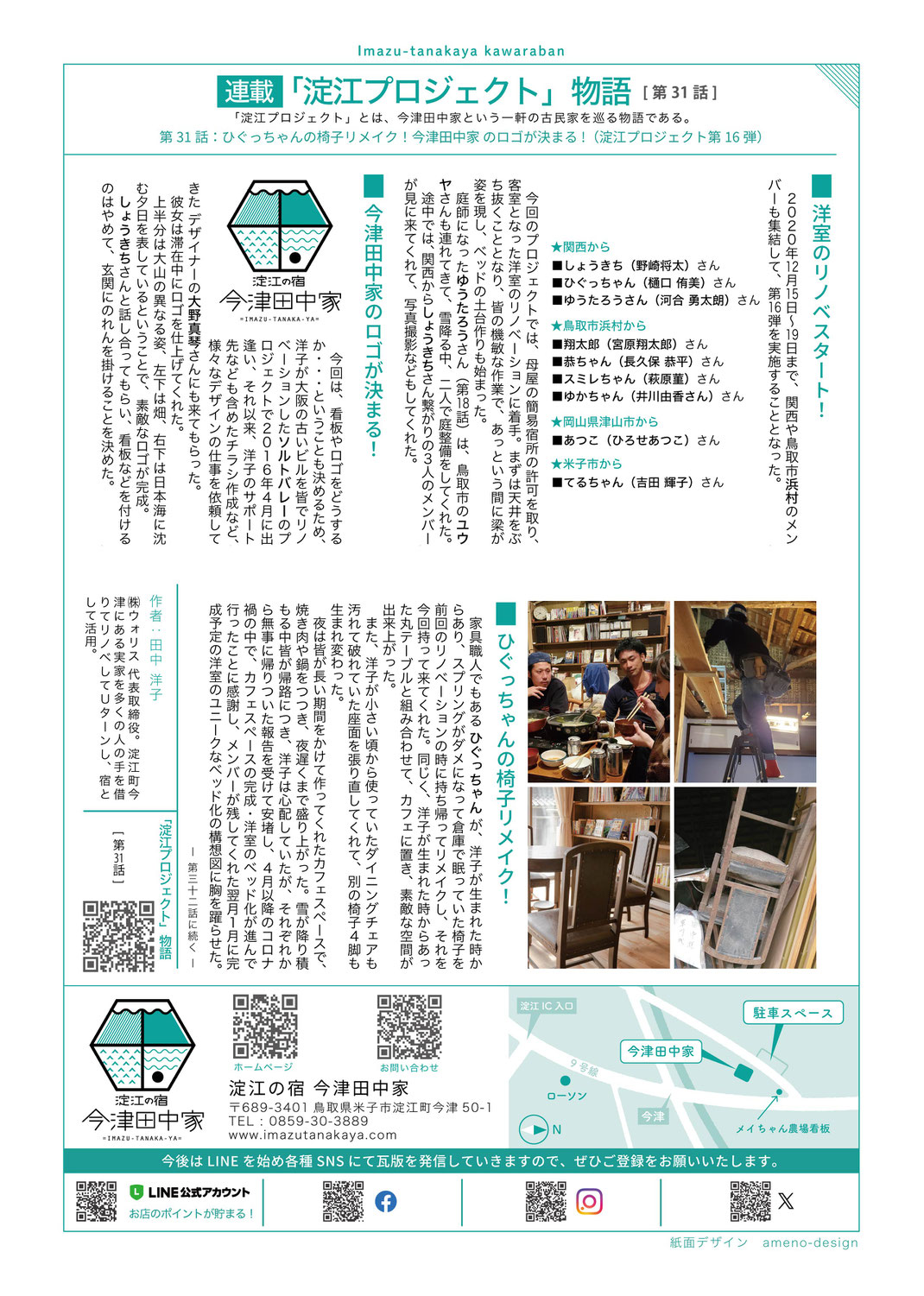1面

絆と信頼を挑戦へ (セカンドホーム 代表 生田 瞳)
今津田中家さんにお世話になるのは3回目。今まではすべてのプログラムに全員で取り組んでいましたが、今回はシャワークライミングを難易度で2コースに分けて楽しみました。キャンプリピート生はインストラクターさんとの信頼関係も育まれ、初対面ではさせてもらえないような挑戦ができたよう。今までで一番楽しかった!との感想も聞いております。初めて参加の子どもたちも、少人数で全員に目が届くからこそできる遊び方をさせていただきました。自然の中での遊びは常に危険と隣り合わせだからこそ、互いの信頼が重要です。コミュニケーションをとり、信頼関係を築いた先にワクワクするような挑戦が待っている。みなさまのおかげで、そんなことも学べる大変有意義なサマーキャンプとなりました。
海とかき氷 (こはる)
今年のキャンプで一番楽しかったのは、海にあそびに行ったことです。なぜかというと海岸で貝がらをさがしたり、海でうきわをつけてプカプカ浮きながらかき氷を食べたりしたからです。水は最初冷たかったけど、なれてくるととても気持ちよかったです。「来年もキャンプにこれたらいいな。」と思いました。
はじめての (けいし )
初めての宿泊行事でしたが、色々なプログラムがあり楽しかったです。一日目は海に行きました。広くて海の水もきれいでした。二日目は、シャワークライミングに行きました。たくさん水着の上から服を着たけれど、水の中に入るとそれでも冷たかったです。岩を上るのに工夫したり川の中を歩くだけでも楽しかったです。三日目は遺跡に行った後、経営ゲームをやりました。出来るだけお金を貯められるよう、一生懸命考えました。
SUMMER CAMP (みさ)
わたしがSUMMER CAMP(鳥取)に行ってたのしかったことは、海に行ったことです。なぜなら、はじめて海に行ったからとふかくてきもちよかったことと、きゅうけい中にかき氷をたべたからです。おわったら、かえってバーバーキューをして、はなびをしてたのしい3日になりました。いい思い出の夏休みになりました。また、つぎの夏休みも行きたいです。
厳しさの中の美しさ (るか)
このキャンプへの参加も今年で三年目です。一年目も二年目も、行くたびに新しい発見がある淀江。今回印象に残ったのは、シャワークライミングです。去年と一昨年はチビッ子たちも混合で行いましたが、今年は引率の先生が増え、初の試み大人だけのガチシャワークライミング。ぐんぐん進み去年の2倍遠い所まで行くことができました。気温は激熱(35℃くらいあったかも。)それでも川は冷たく、むしろ寒いくらいでした。水がとても澄んでいて、キレイな川にしか生息しない、カジカガエルやチョウトンボといった生き物が見られました。神戸のビル群の中では体験することができない荒々しい自然に触れることができて、自然と自分について考え直す、いいきっかけになりました。私は来年の受験に備え忙しい時期にはなりますが、自然と触れあい癒されながら頑張ろうと思います。
2面
最後のサマーキャンプ (ののこ)
私は、このサマーキャンプに参加できるのは今回が最後です。とても楽しいキャンプになりました。
特に楽しかったことはシャワークライミングです。昨年よりも遠くに進むことができた事や昨年より楽しむことができたので最高のシャワークライミングになりました。その日の夕方に、シャワクラの川と昔の人の関わりについていろいろ教えてもらって、昔の人は頭が凄くよかったんだなと、尊敬しました。凄く素敵な川に私たちは行かせてもらったんだなと改めてこのキャンプに参加できて良かったなと感じました。
そして毎日、宿の方が提供してくださったご飯や自分たちで作ったカレーなど、本当においしかったし、作っている時間もとても楽しくて、凄く大切な思い出になりました。
I LOVE 鳥取 ( いつき)
私のサマーキャンプでの一番の思い出は何といっても海水浴である。今年で3回目と なる鳥取での海だが、今年は例年にないほど楽しかったのを昨日のことのように覚え ている。 去年まではあまり沖の方へ行けず、貝やヤドカリを探して遊んでいたが、今年から沖の方へ行くことを許可され、新しくできた友達と、たくましい身体とメガネのイン ストラクターと一緒に魚を探しに行った。そこで、砂浜付近では見れない大きな黒鯛を見つけた。他にもはじめて見る魚や貝がたくさんいて、とても新鮮だった。また鳥取の海では、一緒に魚を見に行ったインストラクターさんと距離も縮まり、新しい友達や新しい思い出がたくさんできた。海遊び以外でも人生初のサイクリングや今までと違うシャワークライミングだったりと語り切れないほどたくさんの思い出ができた。また来年や再来年も鳥取でたくさん思い出を作りたい。
初めてだらけのサマーキャンプ (まさき)
今回私は初めてセカホのキャンプに参加しました。今回のキャンプに参加していたみ んなと仲を深めることができて良かったです。また3日間を通して、一番楽しかったのは、1日目の海と夜にみんなでした花火です。海では初めてシュノーケルを使って潜りました。最初は使い方が分かっていなくて大変でしたが、使い方のコツをつかんで潜ったときは、とても楽しかったです。奥の方まで行った時、見たことがない魚がいたのでびっくりしました。海もきれいだったのでまた行きたいと思いました。海に行った後みんなでバーベキューをしてから花火をしました。海に行った後だったから 疲れていたけれど、みんなで楽しく花火ができたので疲れもなくなりました。
また2日目と3日目に経営ゲームをしました。私は初めてだったので友達にルールを教えてもらいながらやっていたけれどルールが難しくて日にちが足りないくらいでした。ゲームをしているときに毎ターン支払わなくてはいけないお金があることを知 りました。私は会社を経営しようと思っているので、とても勉強になりました。
今回、海プログラム・BBQ・シャワークライミング ・夕飯づくり・花火などに地元の方に加わってもらいました。
・なかやまトレック 杉崎元哉さん 他2名 ・Mimori 松田彩子さん 坂上萌さん・ありがたいご近所さん 山中文男さん
オーダーメード学習塾 SECOND HOME(セカホ)
安心できる場所があるからこそ子どもたちは成長する。一人ひとりに徹底的に寄り添い、やりたい!を全力で支えるオーダーメイド学習塾です。
日々の学習のサポートはもちろん、子どもたちの夢をかなえるお手伝いも行います。キャンプやシーズンスクール、ワクワクあふれるイベントを開催。普段できない経験や出会いを通じて、視野を広げ自国のまた異文化への理解を深めることを大切にしています。
誰もが笑顔あふれる日々を過ごせるよう。“2つめのおうち”セカホは今日も温かい居場所で子どもたちの帰りを待っています。
住所:兵庫県神戸市灘区日尾町2-2-11 六甲第2ビル2階南
電話番号:09042747861
3面

洋子のエチオピア滞在記 Vol.2
コーヒーのお供「コロ」
7月8日の午前中、フクナガエンジニアリングの現地責任者ハブトム(Haftom)さんの車に乗せていただき、福永社長と一緒にエチオピアのフクナガ事務所を訪問しました。椅子付きのエレベータガールが場所を占めていて乗れる人数が少なく、その上、2台のうち1台しか動いていなくて、待ち時間が長かったエレベータにやっと乗り込み、高層ビル22階にあるオフィスに着くと、経理総務事務を担当しておられるティンサエ(Tinsae)さんが私たちを素敵な笑顔で迎えてくださいました。
彼女はコーヒーと共に、コロ(KOLO 麦や小麦、ひよこ豆などの穀物やナッツを炒って塩味をつけたおやつ)を出してくださいました。コロはエチオピアのコーヒーセレモニーでコーヒーと共に提供されるお茶請けで、病みつきになる味わいだと言われています。ハマった私はお土産にたくさん日本に買って帰り、お茶請けの他、スープなどにも入れて楽しみました。
Yoko's Ethiopia Travel Diary Vol.2
Coffee companion "Kolo"
On the morning of July 8th, I was given a ride in the car of Haftom, the local manager of Fukunaga Engineering, and together with President Fukunaga, we visited the Fukunaga office in Ethiopia. The elevator had a chair-equipped elevator girl taking up most of the space, limiting the number of people who could ride, and on top of that, only one of the two elevators was working, so we had to wait a long time before finally getting in and arriving at the office on the 22nd floor of a high-rise building, where Tinsae, who is in charge of accounting and general affairs, welcomed us with a lovely smile.
Along with the coffee, she served kolo (a snack made from roasted grains such as barley, wheat, and chickpeas, as well as nuts, and seasoned with salt.). Kolo is a snack served with coffee at Ethiopian coffee ceremonies, and is said to have an addictive taste. I became addicted to it and bought lots of it as souvenirs to bring back to Japan, and enjoyed it not only as a snack with tea but also in soups and other dishes.
エチオピアの交通事情
ティンサエさんは、中古のトヨタ ハイエースを青く塗装して改造し、後部座席を3列作って定員12名、最大20名くらいギューギューに詰めて乗せて走る「ミニバス(ティンサエさんは「ミニバス」のことを「タクシー」と呼んでおられました)」を二つ乗り継いで通勤されているそうです。今回は機会が無かったので、ミニバスには乗れなかったのですが、次回エチオピア訪問時は、仕事終わりのティンサエさんと一緒にミニバスに乗って彼女のお宅まで帰って泊まらせてもらい、次の朝、もしくは週明けの朝に一緒に通勤するという形でミニバスに乗りたい と彼女にお願いして了承してもらっており、早くエチオピアを再訪して実現できるようにしたいと思っています。
ミニバス以外は、大きな普通のバスなども走っていて、8車線の道路もあったりしますが、渋滞しているところも多かったです。舗装されている道路もありますが、まだでこぼこ道の所もあり、日本車の中古車が溢れ、特にトヨタ ハイラックスがたくさん走っていました。現在は中古の車の輸入が出来なくなったそうで、中国製や韓国製の車が少しずつ増えてきているようです。
鉄道は、アディスアベバ・ジブチ鉄道とライトレールが走っていますが、残念ながら今回は利用する機会がありませんでした。次回訪問時はミニバスはじめ公共交通機関も利用したいと思っています。
今回の滞在では、ハブトムさんなど現地の皆さんの車に乗せていただく以外は、RIDE(スマートフォンアプリを通じて利用者をドライバーとマッチングさせ、移動手段を提供する配車サービス)を使って、移動しました。同じような仕組みに「Uber」があり、2017年にアメリカに滞在したときにはとても便利に使っていて、ドライバーがすぐ待っている所に来てくれたのですが、エチオピアの「RIDE」ではドライバーがすぐに来てくれないことが多かったです。アプリ上では、すぐ近くでウロウロしているのがわかるのですが、ちゃんとスマホを見てくれていないのか、「今どこにいるのか?」という電話やメッセージが入ります。私が伝えるのは難しく、困っている様子を見て、現地のエチオピア人が声をかけてくれて、ドライバーとアムハラ語で直接話して場所を伝えてくれて、ドライバーが私の待っている場所までやって来てくれた!ということもありました。
Transportation in Ethiopia
Tinsae commutes to work by changing between two "minibuses" (Tinsae calls the "minibuses" "taxis"), which are second-hand Toyota Hiace vehicles that have been remodeled and painted blue, with three rows of rear seats to accommodate a maximum of 12 people, or a maximum of 20 people crammed into them. While I didn't have the opportunity to ride a minibus this time, I've asked Tinsae if I could ride the minibus with her after work, return to her house, stay the night, and then commute to work together the next morning or the following week. She agreed, and I hope to return to Ethiopia soon to make this happen.
In Addis Ababa, in addition to minibuses, large regular buses also run, and although there are eight-lane roads, there are many congested areas. Some roads are paved, but others are still bumpy, and there are many used Japanese cars, especially Toyota Hiluxes. It seems that importing used cars is now prohibited, so Chinese and Korean cars are gradually increasing in number.
There are two railways in operation: the Addis Ababa-Djibouti Railway and the light rail, but unfortunately I didn't have a chance to use them this time. Next time I visit, I would like to use minibuses and other public transportation.
During this stay, except when I got a ride in Habtom's or the local people's cars, I used RIDE (a ride-hailing service that matches users with drivers via a smartphone app and provides transportation) to get around. Uber works in a similar way, and I found it very convenient when I stayed in the United States in 2017, with drivers always arriving where I was waiting. However, with RIDE in Ethiopia, drivers often didn't arrive right away. On the app, I could see that they were wandering around nearby, but they didn't seem to be paying attention to their smartphones, as I would get calls and messages asking, "Where are you now?" It was difficult for me to communicate, but when a local Ethiopian saw that I was in trouble, they called out to me, spoke directly to the driver in Amharic, told him the location, and the driver came to where I was waiting!
列に並べておもてなしが手厚い国民性
フクナガエンジニアリングの社長 福永 政弘さんは、ベトナムに続く海外の拠点をエチオピアに決めた基準について、「エチオピア人はミニバスを待つときに、横入りなどをして列を乱したりせず、おとなしく長い列に並んでいること。おもてなしが日本に似ていて、とても親切なこと。」などを挙げておられました。
今回は、同行した皆さんのお陰で、お宅訪問や会社訪問がたくさん体験できたのですが、どこでもとても歓迎されて、きめ細やかなおもてなしを受け、横入りをせず、おとなしく長い列に並べることなども含めて、日本に通じるものがあるなぁと感じたことが何度もあり、エチオピアの人たちとの触れ合いをたくさん楽しむことができました。
The national character of lining up and showing hospitality
When asked why Fukunaga Engineering decided to locate its next overseas base in Ethiopia after Vietnam, President Fukunaga Masahiro cited several criteria, including "When Ethiopians wait for a minibus, they don't cut in line or disrupt the queue, but instead wait quietly in long lines. Their hospitality is similar to that of Japan and they are very kind."
Thanks to the people who accompanied me on this trip, I was able to visit many homes and companies, and I was made to feel very welcome everywhere, with attentive hospitality, and on many occasions I felt there were many similarities with Japan, including the way people don't cut in line and wait quietly in long lines. I really enjoyed interacting with the people of Ethiopia.
淀江の宿今津田中家 2025年度会員募集
瓦版継続発行を応援してくださる会員の皆様を募集しています。お得な会員特典も!ご協力よろしくお願いいたします。
4面